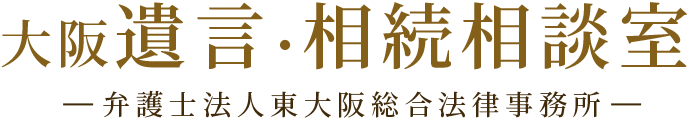- HOME>
- 成年後見
成年後見
成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない方を保護するための制度です。家族や信頼できる人が後見人となり、財産管理や日常生活に必要な契約の代行をおこない、ご本人を保護・支援します。この制度により、高額商品の詐欺被害や誤った契約のリスクを回避することができます。
制度の背景と歴史
現行の成年後見制度は、1999年の民法改正に基づいており、2000年4月に施行されました。それ以前は「禁治産制度」が存在しましたが、その制度は差別的な印象を与えるため改められました。現在の制度では、判断能力の度合いに応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、任意後見制度も導入されています。
成年後見人の役割
成年後見人は、本人の財産管理や生活に関する法的手続き(契約の締結、医療費の支払い、介護契約の締結など)をおこないます。ただし、実際の介護や日常的な食事の世話などは成年後見人の職務ではありません。また、成年後見人は家庭裁判所の監督を受ける必要があります。
成年後見制度が必要な理由
契約や手続きができない場合
認知症などで判断能力が低下すると、銀行での手続きや不動産の売却ができなくなることがあります。成年後見人がいることで、これらの手続きを代行することが可能です。
財産管理の不安を解消
成年後見人は、本人の財産を適切に管理し、詐欺や財産の使い込みから本人を保護します。
成年後見制度の注意点
申立てが必ず承認されるわけではない
誰が成年後見人にふさわしいかは家庭裁判所が判断します。場合によっては、家族ではなく第三者(弁護士や司法書士)が後見人に選ばれることもあります。
報酬の発生
弁護士や司法書士が後見人になる場合、報酬が発生し、それは本人の財産から支払われます。
途中で解任できない
成年後見制度は一度開始されると、途中で解任することが難しいため、慎重な検討が必要です。
家庭裁判所への報告義務
成年後見人は、財産の使い込み防止のため、毎年家庭裁判所へ報告をおこなう義務があります。
できないこともある
成年後見人は全ての行為を代行できるわけではなく、不動産の売却や婚姻など一部の行為は本人の意思が重要視されます。
成年後見人に選ばれる人
成年後見人は、家庭裁判所が本人のために最も適切な保護・支援をおこなえる人物を選任します。家族以外にも、法律や福祉の専門家、福祉関係の公益法人が選ばれることもあります。最近では、地域の市民が後見人を務める「市民後見人」制度も広がっています。
成年後見人等の解任
成年後見人に不正があった場合、家庭裁判所が後見人を解任することが可能です。
成年後見制度の手続きの流れ
step
申立て
成年後見の申立ては、本人や配偶者、四親等内の親族などがおこないます。申立ては本人の住居地を管轄する家庭裁判所でおこないます。
step
審理
書類審査や本人の調査、鑑定がおこなわれ、必要な場合は家庭裁判所が審問をおこないます。
step
審判
家庭裁判所が後見開始の審判をおこない、成年後見人が選任されます。場合によっては後見監督人も選任されます。
step
後見登記
審判確定後、家庭裁判所から法務局に嘱託され、後見開始が登記されます。
相談先と費用
成年後見制度を利用するには、地域の高齢者福祉課や社会福祉協議会、成年後見を業務とするNPOなどに相談できます。申立てにかかる費用は、1万円程度ですが、診断書や鑑定費用を含めると2万円から18万円程度かかります。
成年後見制度を利用する際の注意点

成年後見制度は一度開始されると、基本的に一生涯にわたって利用し続けることになります。このため、利用を決める際には慎重な検討が必要です。また、資産管理が複雑な場合には、家族信託制度などの他の制度もあわせて検討することをおすすめします。