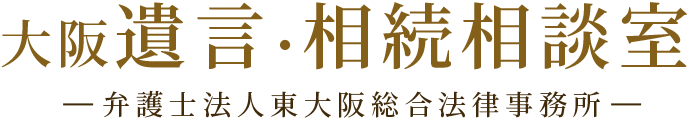- HOME>
- 寄与分
寄与分

寄与分の制度は相続人の間での公平な遺産分割を実現するために重要な制度です。しかし、感情的な対立が起こりやすいため、事前に専門家に相談し、適切な手続きを進めることが大切です。東大阪市の近鉄・JR河内永和駅前にある東大阪総合法律事務所では、経験豊富な弁護士が丁寧にお話をお聞きししっかりとサポートさせていただきますので、寄与分でお悩みの方は、まずはご相談ください。
寄与分とは
寄与分とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合に、その貢献を考慮して法定相続分よりも多くの財産を受け取ることができる制度です。特に、被相続人の介護や事業の手助けを長期間にわたっておこなった相続人が該当することが多いです。通常の法定相続分だけでは、このような貢献が反映されにくいため、寄与分の制度が設けられています。
寄与分が適用される典型的な例
- 相続人の一人が被相続人の介護を無償で長期間おこなった場合
- 被相続人の事業を支援し、その財産を維持・増加させた場合
- など
寄与分と特別寄与料の違い
寄与分とよく似た制度に「特別寄与料」というものがあります。寄与分は相続人にのみ認められる制度ですが、特別寄与料は相続人以外の親族(例えば、長男の嫁など)でも請求することができます。具体的な違いは以下の通りです。
| 項目 | 寄与分 | 特別寄与料 |
|---|---|---|
| 対象者 | 相続人 | 相続人以外の親族 |
| 行為の範囲 | 被相続人の事業支援 財産の維持・増加に関与 |
無償で療養看護などをおこなった場合 |
| 利益 | 相続財産の増加分 | 特別寄与料の支払い |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
寄与分が認められる要件
相続人であること
寄与分は法定相続人のみが請求できます。内縁関係にある配偶者や法定相続人ではない親族は対象外です。相続人は、配偶者や子供、親、兄弟姉妹などが対象となります。
貢献の証明
寄与分が認められるには、相続人が被相続人の財産に対して特別な貢献をしていることが必要です。例えば、無償で介護をおこなったり、被相続人の事業を支えたりしたことが挙げられます。
適切な期間と範囲の貢献
短期間の手助けや一時的な援助では、寄与分が認められにくい場合があります。長期間にわたる支援や介護、財産の維持に関わる貢献が求められます。
寄与分の請求手続き
寄与分を主張するためには、相続人間での遺産分割協議の中で話し合う必要があります。相続人全員が合意し、寄与分を認めれば、寄与分を反映した遺産分割がおこなわれます。しかし、合意に至らない場合には、家庭裁判所での調停や審判手続きを進めることができます。
遺産分割調停
相続人の間で寄与分の合意が得られない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停がおこなわれます。調停では、相続人の意見を聞き、適正な解決策を提示してもらうことが可能です。
遺産分割審判
調停でも合意が得られない場合、最終的には審判によって裁判所が寄与分を含めた遺産分割の内容を決定します。この審判の内容には法的拘束力があり、相続人はその決定に従わなければなりません。
寄与分を主張する際の注意点

寄与分を主張するには、証拠や書類が重要です。例えば、介護の記録や財産に対する貢献を証明する書類を準備しておくことで、寄与分が認められる可能性が高くなります。また、寄与分を主張する期限にも注意が必要で、2023年の民法改正により、相続開始から10年を経過すると寄与分の請求ができなくなる場合があります。