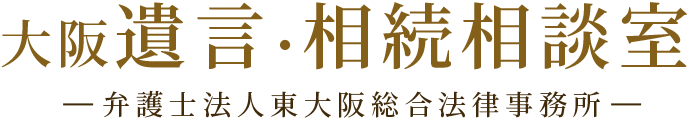- HOME>
- 財産・預貯金の使い込み
財産・預貯金の使い込み
財産・遺産の使い込みとは

遺産の使い込みとは、故人が残した財産を管理していた相続人が、その財産を無断で使用したり、自分の利益に使ったりする行為を指します。使い込みは、故人が亡くなった後に親族が遺産の状態を確認した際、預貯金が予想以上に少ないことで発覚することが一般的です。ただし、故人の生活費や医療費、介護費に充てられていた場合は、使い込みとは認められないことがあります。
財産・預貯金の使い込みの例
- 同居していた相続人が故人の預貯金を引き出し、個人的な目的で使用した
- 故人の生命保険を勝手に解約し、保険金を自分のために使った
- 故人名義の不動産を無断で売却し、その代金を横領した
- 故人の証券口座を利用して株式取引をおこなった
- 故人が所有していたアパートの賃料を着服した
財産・預貯金の使い込みは法律で処罰されない?
通常、人の財産を無断で使用することは窃盗罪や横領罪に該当しますが、親族間の問題ではこれらの罪に対する法的処罰が免除されることが一般的です。そのため、親子や配偶者間での財産の使い込みに対しては刑事罰が適用されることはありません。
財産・預貯金の使い込みが疑われる場合の対処法
使い込みが疑われる場合は、まず本人に対して財産の使用状況の説明を求めることが重要です。
親の生前
親の生前であれば、親本人に確認してもらい、口座の取引履歴を調べることが有効です。
親が亡くなった後
親が亡くなった後で使い込みが疑われる場合は、使い込んだ相続人に対して説明を求めます。しかし、多くの場合、非協力的な態度が取られることが多いため、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、「弁護士会照会」という制度を利用し、銀行などから資料を取り寄せて使い込みの証拠を集めることが可能です。また、税務署に通報するという方法もあります。使い込みが納税額に影響を与える可能性があるため、税務署が調査をおこなうこともあります。
財産・預貯金の使い込みに対処するための方法
話し合いによる解決
使い込みが確認された場合は、まず本人に対して、使った財産の返還を求めます。具体的な金額を明確にし、話し合いによって和解することができれば、その内容を合意書にまとめると良いでしょう。返還が分割払いになる場合は、公正証書を作成し、後々のトラブルを防ぎます。
裁判による解決
話し合いで解決しない場合は、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求の裁判を起こすことができます。不当利得とは、法律上の根拠がない利益を得る行為のことで、使い込まれた財産を返還させるための手段です。
財産・預貯金の使い込みの時効に注意
不当利得返還請求の時効
不当利得返還請求の時効は、「権利行使できると知った時から5年」または「権利が発生してから10年」です。つまり、相続開始から5年以内に請求しなければなりません。時効が成立する前に迅速に行動することが重要です。
不法行為に基づく損害賠償請求の時効
不法行為による損害賠償請求の時効は、「損害および加害者を知った時から3年間」です。使い込みが発覚してから3年以内に請求しないと、請求権が消滅してしまうので注意が必要です。
財産・預貯金の使い込みを防ぐための対策
任意後見制度の利用
親が元気なうちに任意後見契約を結んでおくと、親が認知症などで財産管理ができなくなった際に、信頼できる後見人が親の財産を管理してくれることになります。これにより、相続人が勝手に財産を使い込むことを防ぐことができます。
家族信託の活用

親が財産を第三者に信託し、その第三者が財産を管理する方法です。信託契約は親が認知症になった後も有効であり、信託された財産を不正に使い込まれる心配がなくなります。