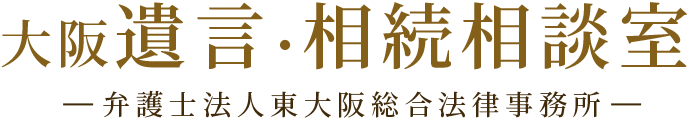- HOME>
- 遺産相続について
遺産相続について
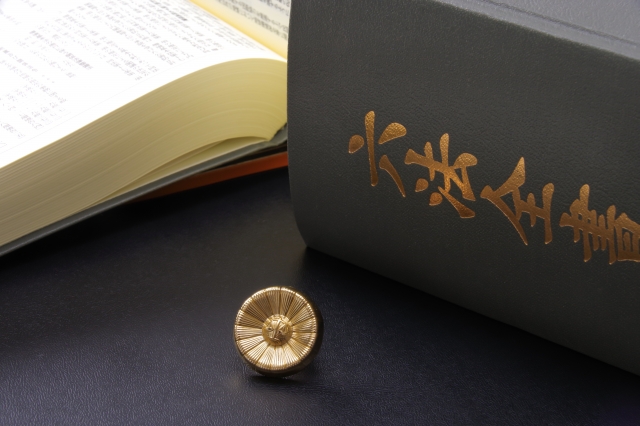
相続とは、故人が生前に所有していた財産や権利、義務を、法律に基づいて特定の人が引き継ぐことを指します。例えば、配偶者や子供が亡くなった人の財産を引き継ぐことが典型的なケースです。遺産相続において、亡くなった人を「被相続人」、財産を受け取る人を「相続人」と呼びます。
相続と遺産
「相続」では、まず遺産の内容を把握することが重要です。遺産とは、被相続人が残した財産全体を指し、その範囲は次のように多岐にわたります。これらの財産が、相続の対象となります。遺産がプラスの財産だけでなく、負債を含む場合もあるため、相続人はその内容をしっかり確認する必要があります。
- 現金や預貯金
- 株式などの有価証券
- 自動車や貴金属などの動産
- 土地や建物などの不動産
- 借入金などの負債
- 賃借権や特許権、著作権などの権利
相続方法について
相続には、主に3つの方法があります。
法定相続
民法に基づき、法律で定められた相続人が一定の割合で財産を受け取る方法です。遺言書がない場合、この法定相続に従って財産を分配します。
遺言による相続
被相続人が生前に遺言書を作成している場合、その遺言書に記載された内容に従って相続がおこなわれます。遺言書は、相続の取り決めにおいて強い効力を持ち、法定相続よりも優先されます。
遺産分割協議による相続
相続人全員が話し合い、遺産の分割方法を決める方法です。各相続人の事情に応じた柔軟な分割が可能です。
遺産を受け取る権利を持つのは誰か?
法定相続人
配偶者や子供、親、兄弟姉妹など、法律で定められた相続人です。相続の順序は、配偶者が常に相続人となり、子供が優先されます。子供がいない場合は親、次いで兄弟姉妹が相続人となります。
受遺者
遺言書に記載されている特定の人物で、被相続人がその人に遺産を譲ることを意図している場合です。
未成年者が相続人となる場合
未成年者が相続人になる場合、その代理人が必要となります。通常、親が未成年者の法定代理人として相続に関わりますが、親も相続人の場合、利益相反の関係が生じる可能性があります。このような場合、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立て、未成年者を代行して遺産分割協議に参加します。
相続財産の分類
相続財産は、大きく分けて「プラスの財産」と「マイナスの財産」に分けられます。相続人は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことになるため、相続放棄や限定承認などの選択肢を検討することも重要となります。
プラスの財産
- 不動産(土地、建物などの不動産資産)
- 預貯金(被相続人名義の銀行口座にある預貯金)
- 有価証券(国債や社債、株式などの金融商品)
- 事業用財産(商売や事業に関連する資産、棚卸資産や売掛債権など)
- 知的財産権(著作権や特許権など)
- 家庭用財産(自動車や貴金属、芸術品などの家庭内財産)
マイナスの財産
- 借入金(住宅ローンや自動車ローンなどの未払い債務)
- 未払金(水道光熱費や通信費、医療費などの未払い分)
- 保証債務(被相続人が連帯保証人になっていた債務)
相続財産の評価方法
相続手続きにおいて、遺産の価値を正確に評価することが求められます。預貯金や有価証券は、その相場や残高を基準に評価されます。一方で、土地や不動産の評価は複数の方法が存在し、時価や路線価を基準に算定されます。不動産の評価方法については、遺産分割や相続税の計算において争いが生じることがあるため、専門家の助言を受けるようにしましょう。また、非上場株式の評価については、会社の規模や業種、株主構成によって異なるため、税理士や弁護士に個別に相談することが重要です。
遺産相続についてお悩みに方は東大阪総合法律事務所にご相談ください

遺産相続は、家族や親族にとって感情的に難しい問題になりがちですが、手続きや財産の評価も複雑です。スムーズに相続を進めるためには、遺言書を準備したり、専門家の助けを借りたりすることが大切です。相続が発生した場合には、法定相続や遺言書による相続、分割協議など、状況に合った方法を選んで進める必要があります。
東大阪市の近鉄・JR河内永和駅前に位置する東大阪総合法律事務所の代表弁護士、滝川正明は弁護士だけでなく、司法書士や土地家屋調査士の資格も持っており、相続に関する手続きをワンストップで対応可能です。遺産相続に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。