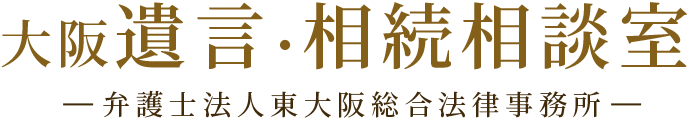- HOME>
- 弁護士による相続問題法律相談
弁護士による相続問題法律相談

相続問題は、家族間の大切な問題であり、法律的な知識が不可欠です。遺産の分配や相続手続きに関するトラブルは、複雑で感情的なものになりがちです。東大阪総合法律事務所では、相続に関する多種多様なケースに対応し、一人ひとりの状況に合わせた適切なアドバイスを提供しています。近鉄・JR河内永和駅前に位置する当事務所は、アクセスも良好で、どなたでも安心してご相談いただけます。相続に関するお悩みや不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
家業を継いだ長男の相続問題
長男として家業を継いでいるが、嫁におこなった妹にも事業資産を分ける必要があるのか?
法律上、相続権は全ての子供に平等に保障されており、妹の相続権を無視することはできません。妹の同意がなければ、事業資産を承継することは難しいです。事業資産の現物分割が困難な場合、金融資産を用意して分割するか、妹への分与を調整することが重要です。この調整には、遺産の評価や生前贈与の有無、親に対する長男の寄与分などが考慮されます。
息子の遺産に含まれる親が預けたお金について
息子名義の預貯金のうち、親が預けた500万円も息子の遺産に含まれるか?
息子名義の預貯金が親の財産であると主張する場合、その500万円が遺産に含まれるかを明確にするために「遺産に関する紛争調停」を申し立てる必要があります。遺産分割調停は遺産であることが前提となるため、まずはその財産が遺産かどうかを確認する手続きが求められます。この調停が不成立の場合、「遺産であることの確認を求める訴え」を提起することができます。
養子縁組した子供と現在の家族の相続問題
元妻との養子縁組をした子供が2人いるが、再婚した現在の家族に相続させたい。どのように対処すべきか?
相続問題を防ぐためには、遺言書の作成が有効です。公正証書遺言として作成すれば、後の紛争を防ぐ手段として適切です。しかし、たとえ遺言書で子供たちに「相続させない」としても、彼らには遺留分請求権があるため、完全に相続を排除することはできません。もし完全に相続させたくない場合、法律的には養子縁組を解消(離縁)することが必要です。
介護をしていたが遺言書がない場合の相続問題
介護をしていたが、遺言書がないため、面倒を見ていなかった姉と遺産を半分ずつ分けることになるのか?
遺言書がない場合、法定相続分に従って遺産は半分ずつ分けられます。たとえ姉が「相続を放棄する」と以前に話していたとしても、法律上それは有効ではありません。しかし、あなたが母親に対して介護や財産管理で大きく貢献していた場合、寄与分の主張を通じて遺産分割の調整が可能です。また、姉との交渉により、相続放棄をさせることも選択肢として考えられます。
自宅の名義変更と相続権について
父が生前に兄に自宅を名義変更しようとしているが、相続後に自宅を売る際、私は権利を持たないのか?
生前に自宅の名義変更がなされれば、兄がその不動産の所有権を持つことになります。そのため、相続前でも兄は自宅を処分する権利があります。ただし、特別受益として、その名義変更が遺産の前渡しであると主張することで、相続時に兄に金銭請求をすることが可能です。しかし、兄が親から経済的援助を受けていた場合、持戻免除(遺産の前渡しを考慮しない)の意思表示があれば、請求ができなくなる可能性があります。
相続放棄後の債権者からの請求対応
相続放棄をした後にも、被相続人の債権者から請求されることはあるか?また、請求された場合にはどう対応すればよいか?
相続放棄が有効であることが前提であれば、相続放棄者は被相続人の債務を支払う義務を免れるはずです。しかし、債権者が相続放棄の無効を主張して請求してくる可能性はあります。この場合、訴訟を通じて相続放棄の有効性を争うこととなります。特に、放棄の際に単純承認がなされた場合や、3か月の熟慮期間を過ぎてから放棄した場合は、相続放棄が無効とされるリスクもあるため、慎重な対応が求められます。
再婚後の相続権の扱い
配偶者と死別した後に再婚した場合でも、相続権に変わりはないか?
相続権は、被相続人が亡くなった時点で確定します。そのため、その後に再婚したとしても、相続権や法定相続分が変更されることはありません。相続に関する権利は被相続人が死亡した時点での配偶者や子供に与えられるため、再婚後の新しい配偶者は影響を受けません。
介護放棄や虐待をおこなった兄に相続させたくない場合
兄が父親に対する介護を放棄し、虐待をしていたため、相続させたくない。どうすればよいか?
介護の放棄や虐待は、相続欠格事由に該当しません。そのため、法的に相続権を排除することは困難です。ただし、兄が父親に強迫をおこない、父親がその結果として遺言書を作成した場合、遺言が無効となる可能性があります。また、被相続人が生前に兄を相続から排除したいという意思を持っていた場合、相続廃除の手続きをおこなうことができますが、すでに亡くなっている場合はその手続きはできません。
子供に借金を相続させたくない場合
夫の死後、借金が発覚したが、未成年の子供に借金を相続させたくない。どうすればよいか?
妻であるご本人が相続放棄をする場合、未成年の子供についても親権者として相続放棄をおこなうことができます。しかし、ご自身が相続する一方で、子供に相続放棄をさせたい場合は利益相反となり、親権者としては放棄できません。この場合、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立て、子供に相続放棄をおこなわせることが必要です。
元夫との子供に相続放棄をさせたい場合
前夫が亡くなり、子供2人に相続放棄をさせたいが、自分が代理で放棄の申請をできるか?

未成年者の相続放棄に関して、複数の子供が相続放棄をする場合、利益相反の問題がないため、親権者であるあなたが代理人として相続放棄の申請をおこなうことが可能です。利益相反がない場合、特別代理人の選任は不要です。