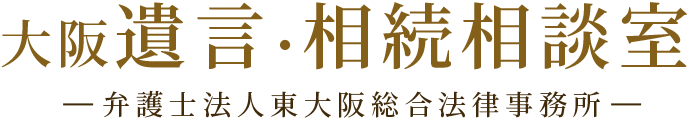- HOME>
- 相続人が行方不明
相続人が行方不明
相続人に行方不明者がいる場合の対応

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要な手続きです。しかし、相続人の中に行方不明者がいる場合、どのように進めるべきか悩むことが多いです。行方不明者がいる場合、次の流れですすめることが必要になります。
行方不明者の住所を特定する
まず、行方不明者の住所を特定する必要があります。相続人の権利は行方不明でも消滅しないため、無視することはできません。行方不明者であっても相続に参加する権利があるため、その所在を特定する必要があります。
住所の特定には、相続人の戸籍謄本を利用します。戸籍附票を請求することで、行方不明者の現住所を確認できます。これにより、連絡が取れる可能性が高まり、協議に参加してもらうことが可能です。
行方不明者への連絡
住所が特定できたら、行方不明者に手紙を送って連絡を試みます。この手紙には、相続が発生したことや遺産分割協議が必要である旨を記載し、相続人としての役割を説明します。
手紙を書く際には、相続人全員の関係図や協議の必要性を丁寧に説明し、相手が内容を理解できるように配慮します。また、電話番号を記載して連絡を促すことも有効です。
行方不明者が見つからない場合の対応
行方不明者が確認できない場合、不在者財産管理人を選任する必要があります。これは、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加し、その財産を管理するための代理人です。
不在者財産管理人の選任手続き
不在者財産管理人は、家庭裁判所に申し立てて選任します。申立人は、他の相続人や行方不明者の利害関係者が行います。不在者財産管理人が選任されれば、その後、行方不明者の代理として遺産分割協議に参加します。
必要な書類
- 不在者財産管理人選任申立書
- 行方不明者および申立人の戸籍謄本
- 不在者財産管理人候補者の戸籍謄本および住民票
- 不在の事実を証明する書類
- 財産目録
行方不明者の失踪宣告と死亡認定
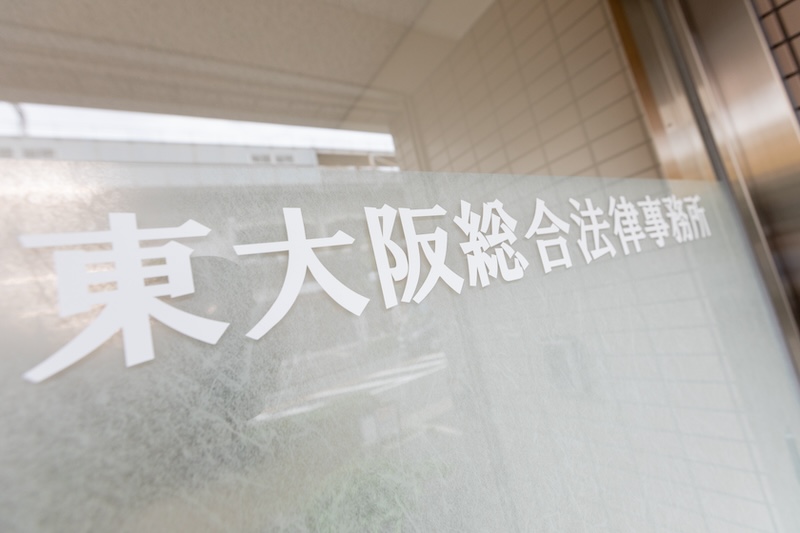
もしも行方不明者が長期間見つからない場合、失踪宣告の申し立てを家庭裁判所におこなうことができます。失踪宣告を受けることで、その行方不明者は死亡と見なされ、遺産分割協議も進めやすくなります。
失踪宣告には2種類
| 普通失踪 | 特別失踪 |
|---|---|
| 行方不明になった日から7年が経過すると、死亡と見なされる手続きです。 | 遭難や災害による生死不明の場合、1年が経過すると死亡と見なされます。 |
不動産相続と行方不明者
行方不明者がいても、不動産の相続登記は可能
遺言書がある場合は遺産分割協議をおこなわなくても登記できます。法定相続分での分割の場合は、共有名義として登記されますが、売却や処分には全員の同意が必要になります。
行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人の選任や失踪宣告などの対応を早めに進めることが、相続手続きを円滑に進めるためは大切です。