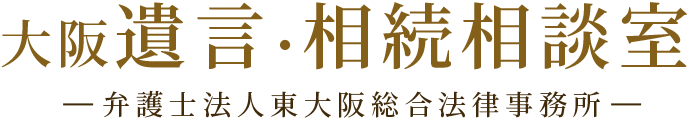- HOME>
- 特別受益
特別受益
特別受益とは
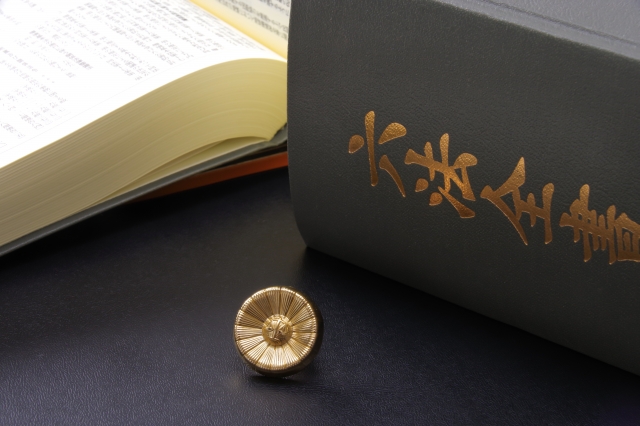
特別受益とは、相続における法的な概念で、被相続人(亡くなった方)から特定の相続人が生前に受けた贈与や、死因贈与、遺贈などの利益を指します。このような受益は、民法第903条に基づき、遺産分割時に考慮されます。特別受益者がいる場合、その受益分を遺産に計上してから、相続財産を分配することになります。これは、相続人間での公平性を保つための制度です。
特別受益の目的
特別受益の主な目的は、遺産分割における不公平を避けることです。たとえば、兄弟が相続人の場合、ある兄が親から多額の生前贈与を受けていたなら、他の兄弟はその贈与分を考慮して遺産を分割してほしいと考えるでしょう。このような場合、特別受益の制度が公平な分配を可能にします。
特別受益の持ち戻しについて
生前贈与や遺贈がおこなわれた場合でも、その受益分を遺産に加算し、遺産を公平に分割するのが「特別受益の持ち戻し」という制度です。ただし、被相続人が「特別受益の持ち戻しをしない」という意思表示を遺言書などで残していれば、持ち戻しはおこなわずに遺産分割が進められます。この意思表示は「持ち戻し免除」と呼ばれ、原則として遺産分割には適用されますが、遺留分には適用されません。
特別受益に該当するケース
特別受益に該当する典型的なケースには以下のようなものがあります。
結婚に関する贈与
結婚時に親から支払われた持参金や支度金などが該当します。結婚に関する贈与は、相続財産の前渡しと見なされる場合があります。
不動産の贈与
親が子どもに自宅の土地や建物を贈与した場合、その価値が特別受益と見なされることがあります。
事業資金の贈与
事業を継ぐための資金や財産(株式や農地など)の贈与も特別受益に該当します。
生前贈与による節税対策
相続税対策で年間110万円以下の金額を贈与する場合も特別受益に該当します。
特別受益に当たらないケース
以下のケースでは、特別受益に当たらないと判断されることがあります。
生命保険金
生命保険金は保険契約に基づく受取人の固有の財産とされ、特別受益には該当しません。ただし、保険金が相続人間で極端な不公平を生じる場合は例外があります。
死亡退職金
死亡退職金は、会社が規定に従って遺族に支払うもので、特別受益には当たりません。
婚資や結納金
結婚に関する婚資や結納金、挙式費用の一部は儀礼的な側面が強いため、特別受益と見なされません。
学資の負担
一般的に、親が子どもの学費を負担するのは普通とされ、特別受益には該当しません。ただし、非常に多額の学費が特定の相続人にだけ支払われた場合は特別受益となる可能性があります。
法改定と特別受益の持ち戻し期間
2019年の民法改正により、特別受益の持ち戻しに関する制度が変更されました。これまで持ち戻しに時効はありませんでしたが、法改正によって、遺留分を計算する際の持ち戻し期間は10年と定められました。これは、被相続人が亡くなる10年以上前におこなわれた贈与については持ち戻しの対象とならないことを意味します。ただし、この10年の期限が適用されるのは遺留分の計算に限られており、遺産分割協議で具体的な相続分を決定する際には、これまで通り特別受益に時効はありません。
配偶者への持ち戻し免除
2019年の改正により、婚姻期間が20年以上の配偶者に対する居住用不動産の贈与や遺贈については、特別受益の持ち戻しが免除される規定が追加されました。これは、遺された配偶者の生活を守るための措置であり、特別な意思表示がなくても適用されます。
特別受益の計算方法
特別受益の持ち戻し計算は、被相続人の遺産に特別受益分を加算してから相続分を決定します。例えば、被相続人の財産が5,000万円あり、特別受益として500万円を受け取っていた場合、みなし相続財産は5,500万円となります。これを元に相続分が計算されます。
特別受益によるトラブル防止

特別受益は、遺産分割の公平性を保つための制度ですが、誤解や感情的な対立が生じることがあります。特別受益を巡るトラブルを避けるためには、弁護士の仲介を利用して遺産分割協議を進めることが有効です。また、遺産分割調停や審判を通じて解決する方法もあります。