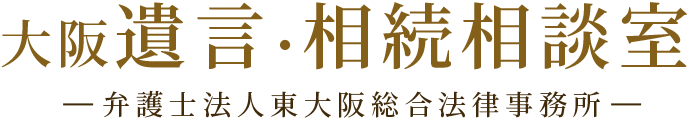- HOME>
- 任意後見
任意後見

任意後見制度は、本人の意志を尊重しつつ、将来的な不安を解消するための重要な制度です。将来に備え、信頼できる任意後見人を選び、適切な計画を立てることが重要となります。
任意後見制度について
任意後見制度は、ご本人が元気なうちに自ら信頼できる人(任意後見人)を選び、将来、判断能力が低下した際に備えて支援を依頼する制度です。この契約は公正証書によっておこなわれ、裁判所が選任した「任意後見監督人」が後見人の活動を監督します。
後見制度の種類
後見制度は、本人の事情や判断能力の程度によって以下の3つに分類されます。
後見
判断能力が著しく低下している場合に、後見人が資産や財産に関する法律行為を代理し、誤っておこなった契約も取り消せます。
補佐
複雑な判断ができなくなる場合に、補佐人が法律行為を代理し、契約の取消権も持つことができます。
補助
判断能力が一部不足している場合に、補助人が法律行為の援助や代理をおこない、必要に応じて取消権を持つことができます。
任意後見と法定後見の違い
| 任意後見制度 |
|
法定後見制度 |
|
|---|
任意後見の利用方法
任意後見契約には、以下の3つの利用方法があります。
即効型
契約後すぐに制度を発動させる方法。
移行型
元気なうちに財産管理や見守り契約を結び、将来必要になったら任意後見契約を発動する方法。
将来型
判断能力が低下してから支援を受けるために契約を結ぶ方法。
特に、日々の事務作業や財産管理が難しくなった際に「移行型任意後見契約」を利用することが多く、この方法では、任意後見人が財産管理を柔軟にサポートします。
任意後見制度のメリットとデメリット
メリット
- 本人の希望を具体的に反映できる。
- 自分で後見人を選べる。
- 後見人の報酬を自由に決められる。
デメリット
- 任意後見監督人の選任と報酬が必要。
- 任意後見人には取消権がないため、誤った契約の取消ができない。
- 死後の手続きには対応できない(死後事務委任契約や遺言が必要)。
任意後見制度は、
高齢化社会において将来の判断能力低下に備える重要な制度

任意後見制度を利用することで、自身の意思を尊重した財産管理や身上監護が可能になります。また、任意後見制度の利用には法的な知識が必要です。適切な契約内容の設定や、将来の後見開始に向けた準備など、専門家のサポートを受けることで、より確実で効果的な対策が可能になります。東大阪総合法律事務所の代表は、現在数名の方の後見人を務めさせていただいており、任意後見制度に関する豊富な実務経験があります。当事務所では、任意後見制度と併せて遺言書作成や財産管理のアドバイスもおこなっています。任意後見制度の利用をお考えの方、また将来の財産管理に不安をお持ちの方は、ぜひ東大阪市の近鉄・JR河内永和駅下車すぐの東大阪総合法律事務所にご相談ください。