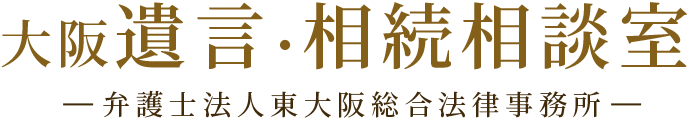- HOME>
- 遺言書作成
遺言書作成
相続は、財産の多寡にかかわらず争いはつきもの、遺言は元気なうちに準備しましょう。
「自分は大した財産がないから、遺言書なんて不要」と思っている方へ

相続争いは財産の大小に関係なく発生することがあります。むしろ、少ない財産であっても、その配分を巡って親族同士が対立してしまうケースが少なくありません。特に、お子さまがいない夫婦の場合、兄弟姉妹の間で話し合いがこじれることが多くあります。こうした事態を防ぐために、元気なうちに遺言書を作成しておくことが大切です。遺言書があれば、相続人の納得を得やすく、トラブルを未然に防ぐ効果があります。
遺言書は正しく作成しなければ意味がない
遺言書は、形式に不備があれば法的効力を持たない可能性があります。たとえば、認知症の方が作成した遺言書は「遺言能力がない」と判断されることがあります。また、自筆証書遺言の場合、書式に誤りがあると効力が失われることもあります。さらに、遺言書が誰にも発見されずに終わることも考えられます。
遺言書は死後に効力を発揮するため、誤りがあっても修正ができません。
必ず法律の専門家に相談し、正確な遺言書を作成することが大切です。
遺言書の主な形式
自筆証書遺言
すべて自筆で書かれた遺言書です。書式に誤りがなく、被相続人の自筆であることが証明できれば問題ありませんが、遺族の間でその真偽を巡って争いが生じることもあります。
公正証書遺言
公証役場で公証人が遺言書を作成します。証人2名が必要で、一部は公証役場に保管されます。この形式の遺言書は、真偽を巡る争いが起こりにくく、最も安心な方法です。
秘密証書遺言
遺言者が署名した遺言書を封印し、公証人と証人2名が署名・押印する形式です。内容は公証人に知られず、ただその存在だけを証明する制度です。
遺言書を作成する流れ
step
相続人および財産内容を確認
戸籍謄本や通帳、不動産の登記簿謄本を基に、相続人と財産内容を確認します。
step
遺言書の内容を決定
誰にどの財産を相続させるかを決めます。この段階で法的アドバイスをおこない、下書きとなる遺言案を作成することも可能です。
step
遺言書の作成
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、作成後に封印し、内容に問題がないか確認します。公正証書遺言の場合は、公証役場での作成をサポートします。
step
遺言書の保管
作成された遺言書を適切な場所に保管します。また、作成後のアドバイスもご提供します。
専門家のアドバイスを受けて、
確実に効力を持つ遺言書を作成しましょう

確実な効力を持つ遺言書は、将来的な相続トラブルを防ぎ、故人の意思を確実に反映させることができます。
しかし、遺言書作成には法的な知識が必要であり、手続きが不十分だと無効になるリスクがあります。そのため、弁護士などの専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。東大阪総合法律事務所では、豊富な経験と専門知識を活かし、確実に効力を持つ遺言書の作成をサポートいたします。クライアント様の状況や希望を丁寧にお聞きし、最適な遺言書の作成をお手伝いします。遺言書作成をお考えの方は、ぜひ東大阪市の近鉄・JR河内永和駅すぐの東大阪総合法律事務所にご相談ください。